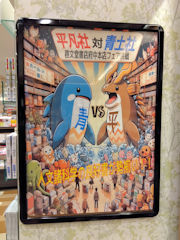桃はこの季節の果物ではないと思いますが、コンビニなどへ行くと桃のフレーバーの商品は季節を問わず、一年中置いてあるような気がします。
 桃の話題はともかく、三省堂書店の成城店で国書刊行会のフェアが開催されていました。題して「若手編集&営業が推す おすすめ選書フェア」です。同社の若手編集部員、営業部員が選んだ書籍のフェアということです。
桃の話題はともかく、三省堂書店の成城店で国書刊行会のフェアが開催されていました。題して「若手編集&営業が推す おすすめ選書フェア」です。同社の若手編集部員、営業部員が選んだ書籍のフェアということです。
 フェア台にはこの画像のようなチラシが置かれていました。A4サイズの裏表にビッシリと、どうしてこの書籍を推しているのか、熱い思いがほとばしっています。こんな熱い編集と営業の両輪で国書刊行会は運営されているのですね。見倣いたいものです。
フェア台にはこの画像のようなチラシが置かれていました。A4サイズの裏表にビッシリと、どうしてこの書籍を推しているのか、熱い思いがほとばしっています。こんな熱い編集と営業の両輪で国書刊行会は運営されているのですね。見倣いたいものです。
否、見倣いたいではなく、見倣わなくてはなりませんね。振り返ってみれば、若いころは、あたしももう少し熱い情熱を持って営業をしていたのかも知れません。そんな灯が消えてしまったのはいつのころでしたでしょうか。
あたしのカバンの中に入っているものです。のど飴もモモ味、MINTIAもモモ味、XYLITOLガムもモモ味という、これでもかというくらいの桃尽くしです。特にMINTIAはカバンの中に入れていると桃の香りが漂うので、それだけでテンションが上がってきます。
ちなみに、香りと言えばあたしのカバンは霊によって匂い袋が入っているのですが、この桃尽くしのポケットには匂い袋は入れておりません。香り同士がぶつかり合うようなことはございませんので、ご安心ください。