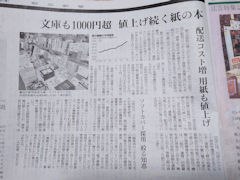現在、日本には出版社が何社くらいあるのかわかりませんが、そのほとんどは東京に本社を置いています。東京以外の地で頑張っている出版社も数多くあるのは知っていますが、出版点数で考えれば過半が東京にあるのは間違いのない事実です。
とはいえ、創業者が東京出身であるわけではありません。むしろ創業者のほとんどは地方から東京に出て来て出版社を立ち上げたのだと思います。そんな創業者の故郷には、その業績を称えた記念館などが建てられていたりします。今日の朝日新聞夕刊にこんな記事が載っていました。
 一見すると、一面全面を使った筑摩書房の広告かと錯覚しそうな紙面です。もちろんそうではなく、筑摩書房の創業者が長野県塩尻出身ということで、地元の図書館が筑摩書房の書籍をすべて取り揃えている、という記事です。塩尻には古田晁記念館もありますから市を挙げて顕彰しているのでしょう。ちなみに古田晁は「ふるた・あきら」と読みます。
一見すると、一面全面を使った筑摩書房の広告かと錯覚しそうな紙面です。もちろんそうではなく、筑摩書房の創業者が長野県塩尻出身ということで、地元の図書館が筑摩書房の書籍をすべて取り揃えている、という記事です。塩尻には古田晁記念館もありますから市を挙げて顕彰しているのでしょう。ちなみに古田晁は「ふるた・あきら」と読みます。
これで思い出したのが、あたしの勤務先です。あたしの勤務先の創業者は秋田県出身で、この数年は洪水や氾濫、決壊などでたびたびニュースにも登場する雄物川沿いです。地元の雄物川図書館にはあたしの勤務先の刊行物が揃っていて、かつて訪問したことがあります。雄物川を訪問する前に立ち寄った角館には新潮社記念文学館がありました。同社の創業者・佐藤義亮(さとう・ぎりょう)が同地の出身だそうです。そう言えば、東北には佐藤姓が多いと聞いたことがあります。
こんな風に出版社の創業者って地元では名士であり、顕彰され記念館や記念文庫が作られるケースがままあるようです。高松には文藝春秋の菊池寛記念館がありますし、諏訪には岩波書店の岩波茂雄ゆかりの信州風樹文庫があります。茅野市の蓼科親湯温泉にはみすずLounge & Barがありますが、これはみすず書房の小尾俊人(おび・としと)が茅野出身だからです。
こういう出版社ゆかりの図書館や記念館を訪ね歩くのも面白いですね。