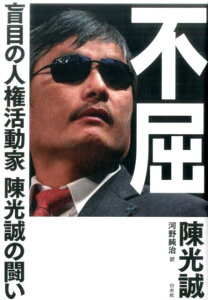この数年話題となっている刺青の件です。
海外からの観光客が増え、そういう人たちが日本国内のプールとか温泉、すぱなどに入ろうとしたときにトラブルが起きている、というところあたりから始まったのではなかったかと記憶しています。
この問題は世代によっても意見が割れるでしょうね。若い人はファッションだと言うでしょうし。
あたし個人の意見としては、日本人は、そもそもが刺青を入れる文化を持っていたわけなので、そんなに嫌悪する必要もないかな、と感じています。どちらかというと、「タトゥーを入れている人にありがちな立ち居振る舞い」の方にムカッとくることの方が多いです。ただし、それに立ち居振る舞いについては、タトゥーの有無とは関係ないのでしょうが……
ただ、やはり歴史的にはこうだったと述べても、現代の日本人のほとんどの人にとって刺青は暴力団、ヤクザというイメージと結びついていて嫌悪感を持つのも理解できます。電車内でもタトゥーをした若い人ってちょっと怖そうな人が多いと思いますので。
一方で、最近の若者はファッションとしてタトゥーを入れているそうですが、ファッションってTPOが大事だと思うので、入れてしまったら消せない、時と場合に応じて取捨選択(付け外し)できないタトゥーをファッションと呼ぶのには抵抗があります。少なくともオシャレだとは思えません。
また「これからはグローバル社会なのだからタトゥーにも理解を」という意見ももっともですが、グローバル社会なんだからこそ海外から来る外国の方には「日本人はタトゥーによいイメージを持っていない」「タトゥーをしていると入場できない施設がある」ということを知っておいてもらいたいと思うのは身勝手なことでしょうか?
時代小説などでは、愛する人の名前を彫った女性が登場したりしますし、現在もそういう刺青をしている人もいるのでしょうが、ちょっとその気持ちは理解できないですね。だって、あまりにも痛いじゃないですか!
そう言えば、「一心如鏡」っていう刺青を入れている人は現在の日本にいるのでしょうか?