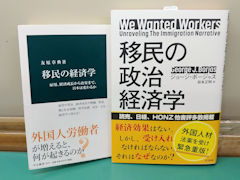今日で四月も終わりというタイミングで『十二月の十日
』を読了。一風変わった短篇集でした。
スッとストーリーに入っていける作品と、これはいったいどういう世界なんだと首をひねり、なかなか作品に入り込みづらいものとがありました。しかし、何とも言えない読後感。よい意味で後味の悪さを感じました。
特に「SG飾り」って何なのよ? 訳者あとがきでは、著者はそれを夢に見た情景から描いたようなことが述べられていましたが、あたしが読みながら頭の中にイメージしていたもので合っているのでしょうか?
それにしても、何の疑問も持たずにこういったものを飾っている人びとの感覚、恐ろしいですね。主人公の子供たちの感性が救いにはなっていますが……
さらに、春真っ盛り、いや各地で既に夏日を記録する日も訪れているこの季節に『秋
』も読了。
主人公を巡る、さまざまなつながりと分断の物語ですね。コロナウイルスで自粛生活を余儀なくされ、なんとかそれを楽しもうとしている人も多いですが、「自粛警察」なる人びとの溝をニュースなどで見るにつけ、主人公のイライラ、焦燥感が身近に迫ってきます。
でも、溝って、結局溝の底まで降りていけば繋がっているわけですよね。決して別々ではなく否応なく繋がっている、切ろうとしても切れないつながり、そんなところが主人公のイライラの原因でもあるのでしょう。そして、現在の一部の日本人の。