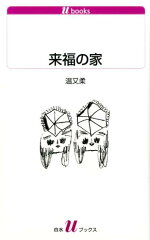中島恵『中国人エリートは日本をめざす』を読んでいて、温又柔『来福の家』を思い出しました。
両書の内容はまったく異なるものです。一方はノンフィクション、一方は小説です。でも次のようなところを読んだときに非常に近しいものを感じました。
友だちは全員日本人で、自分も何も変わらないと思ってきました。私が日本人じゃないことは友だちも知っているんですけど、差別はなかった。でも、母親と一緒に外を歩いているとき、母が大きな声で私に中国語で話しかけるのがすごく嫌で……。できるだけ一緒に外出しないようにしていました。(P.213)
これは小学校に入るときに日本に住む両親の元へやってきて日本の小中高と通ってきた女性の言葉です。さらにこの女性は「両親は日本語の会話に不自由はなかったが、中国人特有の強いアクセントが残っており、それを他人に聞かれるのが恥ずかしかった」ようです。この部分、そしてここから始まる部分は、『来福の家』の主人公、幼いころに台湾から両親ともども来日し、ほとんど日本人として育った主人公が、日本語がうまくない両親に対して持つ感情と一緒です。
こんな感情は一緒なんだな、台湾も大陸も関係ないのかな、そんな気がしました。『中国人エリートは日本をめざす』はほぼ中国大陸から来ている人を取り上げていますし、著者の中島さんの主たる関心もそちらにあります。温又柔さんは日本育ちの台湾の方ですから、小説の主人公も台湾から来た家庭の女の子。そんな二人が出会ったらどんなエピソードが生まれるのか……。もちろん、小説の中で、の話ですけど。
ここに台湾と大陸の近さと遠さがさらに加わるのでしょうか? 楽しみです。